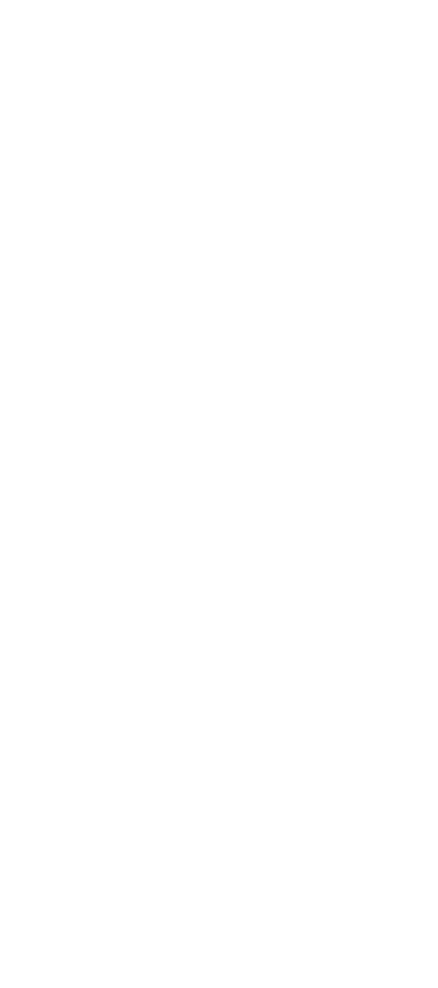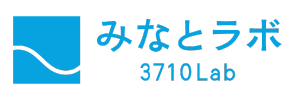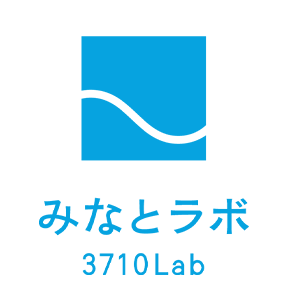春の浜辺で海を眺め、海の向こうを想像していました。
海の向こうにも浜辺で海を眺めて、
こちら側の世界を想像している人がいるかもしれません。
私の視線は果たして海の上をまっすぐに進むのか。
視線にスピードがあるのなら、それは果たしてどのくらいなのか。
私の視線と向こうの人の視線は海の上のどこかで交差するのか。
舳先に人の乗った船がゆっくりと目の前を横切っていきます。
船の通ったところに波が立ち、海は白く光りました。

- インタビュアー
- 海をテーマにした作品をつくってくださり、ありがとうございます。今回は、すでにあった映像作品「光る海」(2021年)を元に、静止画、写真を選んでいったということでしょうか?
- 野口
- 作業としては映像をモニターでみながら静止画を選んでいったのですが、私自身は映像をひとつの風景として眺めながらシャッターを切っていくという感覚でした。
- インタビュアー
- それぞれの場面はどう選んだのでしょうか?
- 野口
- どこか不思議でユーモアのある瞬間、そういうものを繋いでいって、こういう形になりました。映像でみると面白いと感じるのにそれを写真にすると面白くなくなってしまう場面もあって、その秘密はなんだろうと考えながらセレクトしていきました。
- インタビュアー
- そもそもすでにあった映像作品を元に作品をつくろうと思ったきっかけはなんだったのでしょうか?
- 野口
- 元となった「光る海」という映像作品は、2021年に国際交流基金が主催した「距離をめぐる11の物語:日本の現代美術」というオンライン上のグループ展のために制作したもので、コロナ禍で展覧会が中止になったり、気軽に旅が出来なくなった中で一体何かできるのだろうか、と考えたときにつくった作品です。今回お話をいただいて最初に思い浮かんだのは、映像作品を撮影した同じ場所で、今度は写真を撮ってみようということでした。
- インタビュアー
- 写真を撮りはじめたけれど、途中で映像作品を使って写真作品にしようと?
- 野口
- 最初は写真を撮るために海に通っていたのですが、同じ場所に同じカメラを持って通っているうちに、自分がかつて撮影したときと同じ瞬間を探している自分に気がつきました。それならば、すでに存在する映像の中からもうひとつ作品を立ち上げたらどうだろうかと思ったのです。もうひとつは、ウェブ上のプロジェクトということだったので、オンライン上でしか発表したことのない映像作品を別の形で展開していくのは面白いのではとも思いました。
- インタビュアー
- 今回作品をつくってみていかがでしたか?
- 野口
- 眼ではみえなかったものが、カメラを通すとみえてくることってありますよね。今回は望遠レンズで撮影していたこともあって、モニターでみることで初めてみえてくるものがたくさんありました。今回に限らず写真はいつも自分を追い越していってしまうので、私はそれに追いつくために日々を過ごしている感じがあります。
- インタビュアー
- カメラが媒介者になっている感じなのでしょうか?
- 野口
- 自分とカメラと被写体、3つの関係が重要です。この3つの関係が良い形で結ばれると何かが立ち上がっていく感じがします。
- インタビュアー
- 今回の作品づくりが海と自分との関係において、何か変化をもたらしましたか?
- 野口
- 作品づくりそのものよりも、このインタビューを通して自分の中の海を考える機会になったなと思います。



- インタビュアー
- 勝手ですが、イメージする沖縄の海とは少し違う印象でした。
- 野口
- きっと春だったからだと思いますが、私にしか撮れない沖縄の海を撮りたいとも思っていました。撮影したのは2月から3月にかけてなので、まだ泳ぐには早いし、もずくの養殖をしている船もたくさんいました。
- インタビュアー
- 毎回、海にはどのくらい滞在していたんですか?
- 野口
- だいたい午前10時から午後2時くらいまで、ただずーっと海を眺めていました。ちょうどこの時間帯に海が光って綺麗なんです。同じ浜辺にいたのですが、毎日何か起こるんです。でも集中していないと顔を上げたときにはそれはもう終わっていたりする。ただ海を眺め続けるというのは、意外と集中力が必要でした。
- インタビュアー
- ただ眺め続けるって実はすごく難しいですね。
- 野口
- 簡単そうにみえて、意外とできないんですよね。本を読んだり携帯電話をみたり、ついつい何かしたくなってしまう。ただ眺め続けるというのは優雅なようで、実際やってみると修行のようでした。いま振り返るととても贅沢な時間でしたが。
- インタビュアー
- 今回取り組んでみて、もう少し海について考えてみたいという気持ちはありますか?
- 野口
- 前半のインタビューを読み返して、いよいよもうひとつ海について作品をつくらなくてはいけないなと感じました。


- インタビュアー
- 野口さんがただ海を眺めるということを意識してされたように、この「See the Sea」もそれぞれの海を眺めてもらう時間をどう設けられるかなと考えています。
- 野口
- 時間とどう関わっていくのかはとても重要ですよね。私も映像作品をつくるようになって、時間についてよく考えるようになりました。ただ通り過ぎるのではなく見続けてもらうというのは大きな課題ですよね。
- インタビュアー
- みてもらうのは本当に難しいところで、悩みです。
- 野口
- でも今回のプロジェクトはとても良い試みになっているのではないでしょうか。お話をいただいたときは本当に面白いものになるかな、と少し不安に思ったのですが、出来上がった他の方のページを拝見して、ウェブの中に広がりを感じました。ここに何か新しい可能性がありそうな感じがします。
- インタビュアー
- 可能性を感じてくださって、とっても嬉しいです。ただ、やはり何かを伝えようとするときにすごく難しいというか、どこまでどう伝えるべきなのかと。
- 野口
- 何かを伝えようと考えると難しそうですが、それをみた人がふとした瞬間に思い出したりする、そういうきっかけのようなものがつくれるといいですよね。
- インタビュアー
- はい、本当にそう思います。すごく時間がかかるというか、そっと背中を押すようなことって時差があるように思います。
- 野口
- すぐに作用するものもあるし、時間が必要なものもある。みるときの気持ちのコンディションも関係しますよね。けれどウェブサイトは展覧会と違って何度でもみられるから、最初は良くわからなくても、そのうちに意味を持つ瞬間がやってくるのではないでしょうか。だからある程度時間をかけてプロジェクトをやる意味があるんだと思います。
- インタビュアー
- なんだか悩み相談みたいになってしまいましたが、間違っていないんだと背中を押していただきました。ありがとうございました。



- 野口里佳(のぐちりか)
- 1971年、埼玉県生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。在学中から作品制作をはじめ、国内外の展覧会を中心に発表。2002年、第52回芸術選奨文部科学大臣新人賞(美術部門)、2014年、第30回東川賞国内作家賞を受賞。国内での主な個展に「予感」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、2001年)、「飛ぶ夢を見た」(原美術館、2004年)、「光は未来に届く」(IZU PHOTO MUSEUM、2011-2012年)、「不思議な力」(東京都写真美術館、2022-2023年)など。作品は東京国立近代美術館、国立国際美術館、グッゲンハイム美術館、ポンピドゥ・センターなどに収蔵されている。12年間のベルリン滞在を経て、現在沖縄県那覇市在住。好きな海の生き物は「深海の生き物たち」。https://noguchirika.com/