-
レポート
2024.05.27

【開催報告】海とつながるエキシビション「OCEAN LEARNING」展
人イベントものづくりワークショップ海洋デザイン教育
-
レポート
2023.11.07

【開催報告】第二回国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESSー私た...
イベント海洋デザイン教育
-
コラム
2023.06.30

海洋環境デザインプロジェクトとは
環境デザイン海洋デザイン教育
-
レポート
2023.03.20

【開催報告】第一回国際海洋環境デザイン会議(2022年7月30日)
イベント環境デザイン海洋教育
-
連載
2023.03.13
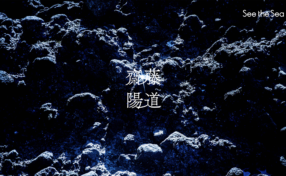
新連載「See the Sea」スタート
写真地域
-
連載
2023.03.13

za-boon.com をリリース!
ZaBoonデザイン
-
コラム
2019.06.26

海洋教育とは? 注目される理由と新学習指導要領での充実
学校探究学習海洋教育海洋デザイン教育
レポート




全体ディスカッション「海洋環境に向き合うデザインのアイデア」
会期も終盤、ここで会議とエキシビションを振り返る時間を設けました。3人のゲストと参加者による話題提供をきっかけにしながら、参加者とともにOCEAN BLINDNESSについての考えを深め、これからの海洋環境デザインのアイデアを描きました。
話題提供者は「国立研究開発法人海洋研究開発機構 JAMSTEC(ジャムステック)」にて海洋科学の普及・広報、アウトリーチ業務など幅広く担当している監物うい子さん。同じくJAMSTECの超先鋭技術開発プログラムの研究員をされている長井裕季子さん。そして、THE NORTH FACEなどを展開するゴールドウィンが新しく展開する「NEUTRALWORKS.(ニュートラルワークス)」の事業部長を務めていられる大坪岳人さん。
まずは監物さんから「JAMSTEC」のご紹介を。文部科学省の管轄で海洋に関する研究、調査など海に関するさまざまな分野を行う研究所です。海の化学を伝えるため、さまざまな広報活動やコラボレーションをされてきた監物さん。そこで感じた「伝わらない、拡がらない」という思い。海洋科学という面で伝えることには難しさがあると言います。だからこそ「デザインの力」が重要だと感じられています。
次は「有孔虫」の研究をしている長井さん。海洋生物を探って、さまざまな生き物の生き様を知ることが重要なのだと言います。その生き物が生きるためにしている工夫がデザインにも活かされるんじゃないかなとのことです。
実は商船学を学んでいたという大坪さん。航海士の免許もお持ちとのこと。お仕事はその方向には進まず、アパレル、ウェアのお仕事に従事されています。洋服は圧倒的にものが捨てられているという現状があり、どのように循環させ、ゆりかごから墓場までどうフォローしていけるのかを考え、動いていらっしゃいます。お話しの中ででてきた大坪さんが大切にしている「自分事/他人事」という考え。自分事にすることの難しさを感じるとき、「めちゃくちゃ大事な他人事」ととらえてみるというのです。100年スパンで考えると、おじいちゃんから孫くらいの時間です。そう考えると意外と近く感じられ、未来を身近なところから描けるのではと。そのほかにも、循環はコミュニケーションを変えるだけでできることがあり、循環とはループさせるだけではないと。使われていないとか、廃棄されるものを利用するということも1つの形です。
ここからは3名のゲストと会場で「OCEAN BLINDNESS」を考えます。私たちは海の恩恵をもらいながら知らないことばかりです。「なぜ、海を知らないといけないんだろう」という問いを探っていく方向にに。
「自分は海を知っていると自信を持っていえますか」と長井さんにみなとラボスタッフから鋭い質問が。「海の包容力からするとまだまだ全然」と話す長井さん。知らないの解像度が高く、知らないということを知っているからこそ言える一言です。結局、海が好きだなということが原動力になります。そのためには、みんなの中に楽しいという気持ちがあってこそ。知らなくても地球にとって良いことや、無意識で良いことになっていたというようなデザインができたらいいですよね。そういうことで理解のボトムアップがなされていくのだろうと思います。結局何かを起こしていくには個人から。面白そうという興味に勝るものはないということです。これは海だけに言えることではないですね。
大坪さんからは「海のことは知らないけど、海の中にあるデザインや仕組みはいろんなものに活かせそうだから知りたい」。監物さんからも「こういう研究をしていますというのが知られていないことが多いんです。知ったら面白いと思ってくれる人にどう会いにいけるか。それがつながっているチャンネルがない。やってる人だけが知っているというこの状況は良くない」と。専門家と企業と私たちのような団体がつながっていける仕組みや場をみなとラボを中心につくっていきたいなと思いました。そういうひとつひとつが「OCEAN BLINDNESS」への突破口なのかもしれません。これからもこうした交流は続きます。次はみなさんもぜひ。



写真家・津田 直とみなとラボ代表・田口康大によるトーク「Oceanscape As Dialogue」
2つ目のプログラムは、写真家・津田直さんとみなとラボ・田口によるトークでした。津田さんとは今年のはじめから人類が自然・海とどのような関わりをしてきたのか、その源流を探り、共生のあり方を育むためのプログラム「海の対話プロジェクト」の開発をおこなってきました。どこに行くか、何をみるか、どんなプログラムができうるのかなど打ち合わせを何度もおこない、北海道・オホーツク海沿岸でのフィールドワークを5月に実施。そこで海、森、川、遺跡を訪れ、いにしえの人々が暮らした地に立ち、海を眺めました。
それらの経験の中間報告をデザイン会議では実施。小展示では、フィールドワークとその後再び訪れた根室で撮影された写真5点を「Starting from Lines Drawn by Nature(引かれた線の上に立つ)」というタイトルのもと展示。
トークではフィールドワークでの体験、それを経て改めて考えたこと、出てきた言葉、来春予定しているワークショップについて語らいました。まずはじめに小展示に寄せて書かれた津田さんの文章を本人みずから朗読されました。この時間で会場の雰囲気がグッと引き締まったのを感じました。
写真をスライドみながらいくつかのキーワードが投げかけられます。タイトルにも入っているラインという言葉。海に出合っていこうとするとき、ひとりで受け取るのは無理がある。点ではなく、ラインで物事を考えるという視点が大切なのだと言います。海に引かれた無数の線が海をみているという共同体的な考え。こういった考えをされるとき、我々とは少し違った「単位」で物事をみているなと思います。5年、10年という時間ではなく、最低でも千年と話す津田さん。そして、“個=I=私”ではなく”We”という視点。自然と深い対話をしていた動物や人のみえない時間軸があり、そういう彼らに体を重ねていくことで人間を忘れ、海になることができるのだとか。私を主語に話してしまうと、自然から離れてしまう。普段私たちはそうした考えの元、暮らしています。そうしたとき、自然とどうつながっていけるのか。
そういうことをワークショップでかたちにできないかと話は次の展開へ。
それは、森を経由した海という回路を子どもたちの中に育てていきたいという思いです。1日の中で森と海を体験することで、森を知った状態で海に立つことができます。自然環境の中に立つことで現れる線は杓子定規にはいきません。きっとこうなると先を決めない状態は、その状況でベストを出すということです。津田さん自身がそうされてきたから言えることです。
前に進むことを求めるのではなく、自分のペースで表現できるようなワークショップの形が見えてきました。つまりは原点にかえろうということ。自分の時間を掴みなおす時間にしたいと田口。津田さんとのやりとりはここで終わりではない。これからも対話を続け、アウトプットし、みなさんとも共有できる形で残し、伝えていきたいと改めて思いました。


