-
レポート
2024.05.27

【開催報告】海とつながるエキシビション「OCEAN LEARNING」展
人イベントものづくりワークショップ海洋デザイン教育
-
レポート
2023.11.07

【開催報告】第二回国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESSー私た...
イベント海洋デザイン教育
-
コラム
2023.06.30

海洋環境デザインプロジェクトとは
環境デザイン海洋デザイン教育
-
レポート
2023.03.20

【開催報告】第一回国際海洋環境デザイン会議(2022年7月30日)
イベント環境デザイン海洋教育
-
連載
2023.03.13
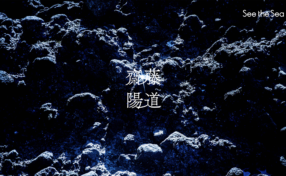
新連載「See the Sea」スタート
写真地域
-
連載
2023.03.13

za-boon.com をリリース!
ZaBoonデザイン
-
コラム
2019.06.26

海洋教育とは? 注目される理由と新学習指導要領での充実
学校探究学習海洋教育海洋デザイン教育
コラム

昨日(前編)に引き続き、今日は昼間の蒲生。
蒲生を守る会が約45年間続けている月に一度の鳥類生態調査の日だ。それに同行しながら撮った写真を、ひたすら並べていこうと思う。4月下旬だが、日差しが強く、昨夜と比べとても暑く感じる

蒲生干潟の全体像を把握するために、まずは、熊谷先生が描いた干潟のイラストマップを見ていただきたい。当日は、この地図をぐるっと反時計回りに歩いた。地図右上の陸地には、現在福島まで続く防潮堤が建設中なので、写真を見る際もそれをランドマークに、頭の中で全体像を思い浮かべてほしい。

蒲生を守る会による『ハンドブック2004』より
蒲生は、比較的狭い範囲の中に、様々な動植物が共生しているのが特徴だ。狭い、とはいえ、調査には4時間かかる。学術研究で一般的用いられている方法で調査をしようと思うと、あまりに大変なので、これでも簡便な調査ということだ。
しかし「一定のやり方で、ずっと続けていこう。みんなでそう決めました」と、熊谷先生は語る。同じやり方で長年続けてきたからこそ、震災前後の比較、回復の軌跡を辿ることもできた。

順に各ポイントをめぐる

流木。とても天気が良く、日差しがキレイだ。

干潟の向こう側(海に近い方)の浜辺に、カカシのようなものが見える。誰が作ったのだろうか。

昨晩ゴカイを観察したあたり。北側の遠目に、仙台港のコンビナートなどが見える。

釣りを楽しむ人も。

小さな魚が。

福島まで続く新たな防潮堤の近くにユリカモメの群れが



新しくできた市の下水処理場


人々との絶妙な距離感

満潮時にはこの辺りにも海水があったことがわかる、波の跡、groove、溝
ユリカモメ に見とれている間に、他のみんなが先に進んでしまった。
後を追いかける。
途中、くるぶしまで浸かるほどの深さの水路のようなものがある。周りの石の形状から、人工的に設置されたと思われる。しかし、その石にはフジツボがビッシリとくっ付いている。






北の方に林が見える。あのあたりが、野鳥の営巣地区らしい。

先ほど遠目から見たカカシ。向こう側に、守る会のみなさんが見える。

おもむろに、革靴が

金属製の棚が流れ着いたようだ。向こう側に見えるのが、福島まで続く防潮堤の先端。

だいぶ海に近いところまで来た。守る会の皆さんが野鳥の観察・調査を熱心にしている。

陸側を見ると、津波にも耐えた松が見えた
ちょうど、予定コースの半分。イラストマップの海岸の真ん中あたりに来ただろうか。

南・福島方面(マップの右サイド)

北・仙台港方面(マップの左サイド)


調査後半、野鳥の営巣地区に近づく。


地面に草が増えてきた。

コウボウムギ。



遠くから営巣地区を観察。気迫すら感じる。
途中、水質調査も行う。




蒲生はサーファーにも人気の海

この高台の上には駐車場があり、津波の際はそこで難を逃れた人もいたそうだ。


池のある地区に分け入る

今では植物が生い茂っているが、震災後はみななくなったらしい。しかし、驚くべき速さで回復をしたものも多い。根が残っていたということか。

野鳥の調査はもちろん、ここでも水質調査をしている。

震災前に作られた防潮堤の上を歩く。左サイドが干潟、右サイドが養魚場。新しい防潮堤は当初左サイドの干潟を潰す形で建設が予定されていた。守る会などの訴えにより、現在では右サイド(内陸寄り)に建設する予定になっている。

養魚場。鴨の群れがいる。ここが、防潮堤によって埋められることになる(一部再開予定もあり)。




防潮堤の上を歩きながら、干潟を眺めた。


ヒメオドリコソウ。 通常は上段のようなピンク色をしている。蒲生には、このピンク色がなくなった白色変異体が生えている。蒲生七不思議の一つだそうだ(他の6つはなんだろうか)。

調査結果が書き込まれた地図。 どの地区でどの鳥を何羽見つけたか、記録している。蒲生では約50種の野鳥が定期的に観察され(震災後は減少)、稀なものも含めれば約150種が観察される。
調査を終えて、その結果や今後のことについて、守る会の人たちが話をしていた。

1970年代、当時の仙台港建設計画では、干潟の全てを埋め立てて国際港にする予定だった。半分以上の干潟は埋め立てられたが、1973年、守る会の活動や世論の後押しにより、残った干潟とその周辺が特別鳥獣保護区に指定され、埋め立てが防がれた。蒲生干潟に降り立つシギやチドリは、ロシアから東南アジアに渡る際、蒲生を訪れている。
干潟にとっての危機は、開発だけではない。サーフィン、釣り人、犬の散歩、潮干狩りなど、マナーが悪ければ、全てが希少生物の驚異になる。蒲生を守る会は、あまりホームページなどで「広く」広報を行っているわけではない。むやみに人が来すぎることも、干潟の状況を悪化させるかもしれない。
しかし、同時に、むやみに人を遠ざけたいとも思っていない。「鳥か人か」という選択ではなく、「鳥も人も」という考え方だ(『蒲生を守る会だより』No. 62. 2009年12月22日)。人の立ち入りを禁止している干潟もあるが、蒲生の魅力は、人が入れることでもある。守る会では、営巣地区に立ち入り禁止のロープを貼るなど、人が集うことと保全の両方を可能にできるような対策もしている。
様々な人が参加することができる自然観察会はこれまでに約180回行われ、震災後もNPOなどと共同でその活動を継続している。
環境問題に関する行動のあり方として “Think globally, act locally” という言葉があるが、熊谷先生はその言葉に疑問を感じるようになったという。『蒲生を守る会だより』(No. 66. 2015年10月15日)で、次のように語っている。
「私は “Think locally, act locally” の精神で行動しようと思っています」
時勢に左右されず、あくまでも、ボトムアップの精神で活動していく。それを継続し続けてきた、静かな強さと優しさのようなものを、調査会に同行して感じた。この積み重ねが、しかし、決してローカルにとどまることのない、希望のようなものも見せてくれている。蒲生を見て僕が感じたのは、そのようなことだった。
防潮堤の工事、下水処理場、サーファー、釣り人。その隣に、絶妙な距離感で、野鳥や、草木や、水棲生物たちが存在している。
共生と断絶が、その空間に共在していた。
そのバランスは、一つ間違えば崩れてしまうかもしれないけれども、ギリギリのところで、成立しているように見える。それは、「自然の声」を聞き続けてきた人たちが自分たちの声で訴え続けてきたこと、「自然の声」をトランスレートし続けてきたことによって、実現している。様々な人工物があっても、生き物がそこに住むことが、ギリギリできている。生き物の力強さと、それを見守る人たちによる配慮が、共生と断絶の共在を可能にしている。
脳の研究をしている僕からすると、ヒトの振る舞いもまた、広義の自然現象の一部でもある。蒲生干潟のさらに内陸には、伊達政宗の頃に開かれた貞山運河がある。人は昔から、自然と共存してきたとも言えるし、緩やかに搾取し続けてきたとも言える。前世紀に入り、人の産業活動は明確に自然破壊と呼ばれるようになった。明らかに人の手が入った蒲生の風景も、80年代生まれの僕にとっては、かえって「自然」な風景にも見える。蒲生に立つと、自然の声と人の声、両方が聞こえる気がする。自然と人工物の境界とは何か。人間と他の生物との境界とは何か。そのようなことに思いを馳せたくなる風景だった。震災の影響は、さらに、災害から人を守ることと、自然を守ること、復興、様々な政治的な問題を突きつけ、自然の声と人の声の複雑さが増したのだろうと想像する。現在のところ、それらを解決する答えは、僕の中には、ない。
ただ、この複雑な感情を誘起する蒲生の風景は、残って欲しいと願っている。
- 取材:
- 3710LAB
- 文・写真:
- 菅野 康太


