-
レポート
2024.05.27

【開催報告】海とつながるエキシビション「OCEAN LEARNING」展
人イベントものづくりワークショップ海洋デザイン教育
-
レポート
2023.11.07

【開催報告】第二回国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESSー私た...
イベント海洋デザイン教育
-
コラム
2023.06.30

海洋環境デザインプロジェクトとは
環境デザイン海洋デザイン教育
-
レポート
2023.03.20

【開催報告】第一回国際海洋環境デザイン会議(2022年7月30日)
イベント環境デザイン海洋教育
-
連載
2023.03.13
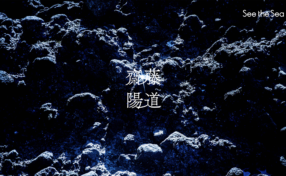
新連載「See the Sea」スタート
写真地域
-
連載
2023.03.13

za-boon.com をリリース!
ZaBoonデザイン
-
コラム
2019.06.26

海洋教育とは? 注目される理由と新学習指導要領での充実
学校探究学習海洋教育海洋デザイン教育
コラム

88年の歴史を刻んだ水族館
―――この度は、3710Lab初のインタビューをお受けいただきありがとうございます。まず、88年続いたマリンピア松島水族館(以下、松島水族館)が残念ながら2ヶ月前に閉館されたわけですが(※取材は2015年7月) 、まずは、水族館の歴史について教えていただけますか。
西條:ありがとうございます。元々は、昭和2年(1927年)に民営の水族館として開館してから、私の祖父が経営を引き継いだのが昭和44年(1969年)でした。それまで祖父は運送業をやっていたんですけど、たまたま松島水族館が経営の譲渡を考えていらっしゃるというタイミングで、ご縁があったようです。

閉館後の松島水族館にて、西條博也さん [写真:創業当時の河北新報の写真など]
――随分前のこととなりますが、創業当時、この水族館はどのように地域に受け入れられていったのでしょうか。
西條:昭和2年ってほとんど資料が残っていないんですが、80周年記念の際に色々と調べまして。地元の河北新報の昭和2年4月2日版に、水族館オープンの記事が載っていますね。同年、いまのJR仙石線(仙台と石巻をつなぐ路線)の前身となる私鉄・宮城電鉄が開通したんです。それを機に県や町がこぞって松島の観光推進をするようになりまして、その一環でこの松島水族館ができたんだと思います。

仙石線・松島海岸駅の目の前に位置した水族館
――はじめから観光と結びついた場所だったんですね。日本で2番目にできた水族館と聞きましたが。
西條:最も古いのが富山県の魚津水族館ですね。水族館自体はそれより前にも存在しましたので、営業時は「現存する日本で2番目に古い水族館」と言っていました。当時としては、循環ろ過システムを海外から日本に取り入れるなど、近代的な設備を導入していったそうです。また、海の生物に限らず、クジャクや小鳥など、動物園の機能も持ち合わせていました。
――それから80年以上の歳月が経るわけですが、閉館の最大の理由は何だったのでしょうか。
西條:やはり老朽化ですね。さすがに昭和2年の建物はありませんでしたが、最も古い場所では昭和47年頃の建物がまだ残っていた。そこに震災の影響も加わり、維持が難しくなってきたことが理由です。もちろん建て替えの計画は20年くらい前から進んでいたのですが、もともと土地が県有地だったこともあり、松島という土地の性質上、文化財や景観の面でなかなか新たな拡張ができず、生き物たちの受け入れ先がつくれないなど、さまざまな問題がありました。
Hello, Goodbye. 松島水族館


Webサイト『Hello, Goodbye. 松島水族館』より
――水族館閉館までのメモリアルを記録したWebサイト、『Hello, Goodbye. 松島水族館』
(http://goodbye-suizokukan.jp/)を拝見しました。これ、もう、すごくいいですよね。
西條:はい、すごくいいんです。有志の方々から「やらせてほしい」と声をかけられ、皆さんの尽力によって生まれたサイトなのですが、わたしたちとしては本当にありがたいものでした。
――どんな方々が関わられていたのでしょうか。
西條:毎年8月に松島で花火大会があったのですが、震災後は地盤沈下や安全性の問題で開催できなくなってしまったんです。その際に、何か地域のお祭りを復活させたいと町の内外から有志の方が集まり、「松島流灯会 海の盆」というイベントが始まったんです。そこで色々な方と出会っていったなかで、松島水族館に共感してくださった方のひとりが、福島県相馬出身の方だったんですが、普段映像の仕事をされているということで、企画を持ちかけてくれたんですね。


Webサイト『Hello, Goodbye. 松島水族館』より
――どれもたくさんの思い出にあふれていて、見ているだけで涙が……。
西條:ここに写っている写真や映像にすべてが集約されていて…、あの風景に突き動かされて、閉館まで乗り切れたというところもありますね。ここに小さい頃にやってきてくれた方が、大人になって子どもを連れてきてくれたり、そうした何世代もの記憶が詰まった場所なんだということにあらためて気付かされました。また、八木山動物園さんと一緒に、シールにメッセージを残してもらうという企画を行ったんですが、それも3000枚近くのシールにお客さんの声が集まりました。閉館する1年前くらいから本当にたくさんの人が来てくれて……、やっぱり寂しいですけどね、今でも。

2015年7月、解体工事中の水族館にて
震災、生き物の死、そして再開
――震災時は水族館にも大変な被害があったと思いますが、震災時の様子を教えていただけますか。
西條:ここ松島にも最大で1.8mの津波が来ましたから、建物全体を管理する中央電気制御室などは防潮板を越えてやられてしまい、2つの建物のうち新館の機能がほとんどストップしてしまいました。最も被害が大きかったのが水槽内の循環装置で、水温や水質の維持管理ができなくなったことで、マンボウやコマッコウイルカ、クラゲが次々と死に、200匹近くのイワシなど小さい魚も全滅でした。6匹いたビーバーも、海水と泥をかぶったために脱水症と低体温症で死んでしまいましたね。
――復旧作業がとても早かった、と河北新報などの記事で拝見しました。
西條:直後は途方に暮れましたが、考える余裕もなかったというのが実際のところです。うちの飼育員は本当に生き物たちのことを大事に思っていて、翌日からすぐに復旧作業に取りかかりました。震災直後は、毎日泥をかきあげながら、備蓄してあった冷凍のエサを生き物たちに与えて、発電機で電力をつくって、という、最低限のライフラインでなんとかしのぐことができました。幸いにも、「宮城県沖地震は10年以内に99%の確率で起こる」と昔から言われていましたから、当館にも発電機や備蓄などの準備があったんです。
――再開はその1ヶ月後だったとのことですが、再オープンの日はどんな様子だったのでしょうか。
西條:2011年の4月23日に再開したのですが、あの頃はまだ傷跡が深くて、テレビやラジオを付けても深刻な話ばかりの中、ここで開いてしまってもいいのかな、という葛藤がこちらにもありました。どれだけお客さんが来るか不安だったのですが、1000人近くのお客さんに来ていただけました。
その中でもね、被災して、松島周辺の親戚に身を寄せていたお年寄りの方とお孫さんが来てくれたんです。そのおばあさん自身は、津波で娘を失ったという状態だったので、正直、「水族館なんか来たくなかった」と仰っていて。でもね、孫が喜んでくれて、その子の笑顔を見ておばあさんも笑顔になったという、笑顔の連鎖みたいなものがあったことを知って。それは、再開して良かった、と実感できた最大の瞬間でしたね。
水族館は、学びと興味を誘う窓口
――祖母から孫へ、託すものがあったのでしょうね。松島水族館では、どんなことを子どもたちに伝えようとしてきたのでしょうか
西條:小さい水族館だった分、最も大事にしていたのは生き物との「距離の近さ」です。基本的には柵や枠をあまり作らず、ペンギンが散歩している様子を間近で見ることができたり、ヒトデやナマコに直接さわれるタッチプールがあったりなど、手を伸ばせば触れられる環境であることを常に意識していました。そうした距離感から、生き物の息づかいだとか、よりダイレクトな経験を感じ取ってほしいなと思っていて。実際に生き物に触れたときの子どもたちの目って、すごく新鮮で、それまでと全く違うんですよ。
――そうした体験を生み出す「水族館」という場所は、社会の中でどんな存在なのでしょうか。
西條:ひとつには、興味の入り口というか、学びへの窓口的な機能があると思います。海にどんな生き物が住んでいるのかなんて、おそらく海の近くで暮らしていない限り、想像がつかないでしょう。松島水族館では地元の漁師さんと水族館のスタッフと一緒に地引き網の体験イベントなんかを行っていて、「ほら、こんなに生き物がいるんだよ」と子どもたちに教える機会をつくっていました。自ら海に入っていく体験というのは、ただ見て終わるよりもずっと多くのことを学べるんですね。
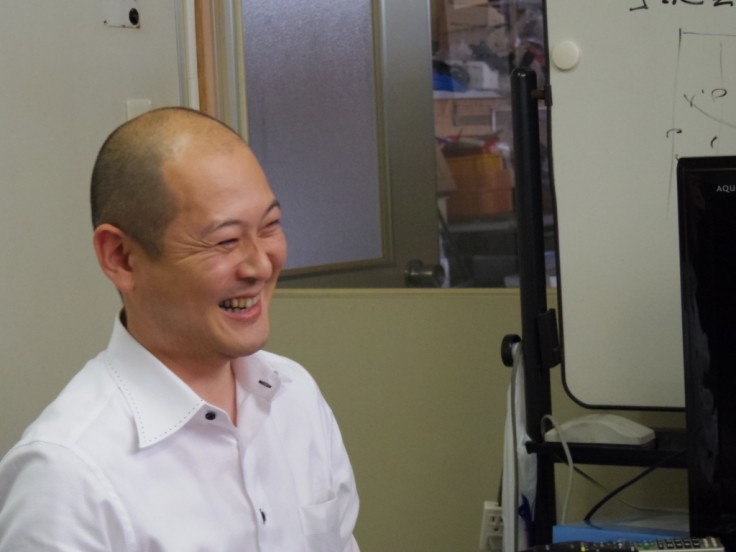
――西條さん自身にとって、子どもの頃の水族館というのはどんな存在でしたか?
西條:祖父の代から家族が働いていたので、それこそかなりの頻度で通っていて、当時はだいぶ飽きてもいました(笑)。そんなときは水族館の目の前の海岸に出かけていって、カニを捕って遊んだり、潮の満ち引きをずっと見ていたりしていましたね。そう考えると、実際に「体を使って、海と遊ぶ」という行為に惹かれていたのかもしれません。その意味でも、松島は本当にいいロケーションなんですよ。
地域に根ざした学びの場をつくっていきたい
――以前、松島水族館閉館後は、海に関わる社会教育施設をつくる意向はあるとニュースで拝見し、非常に興味を持っていたのですが、具体的にはどのような計画があるのでしょうか。
西條:たとえば、海を目前にした立地や、地元の漁師さんや東北大の先生がたとのつながりを活かして、海の生態や文化の体験や観察ができるような施設を考えています。いまは震災で生態系が変わってしまったアマモの再生プロジェクトなどが進んでいるのですが、なかなか議論をするにも拠点がないので、そうした取り組みの受け皿となり、フィールドワークも同時に行えるようなラボ機能も果たせればいいな、と。ただ、体験ベースの施設となると、一民間企業ではなかなか負担しきれないので、現在は公的機関への助成などを募っている段階です。
――それは、わたしたち3710Labとしても今後目指したいプラットホームのあり方のひとつです。そうした地域を絡めた取り組みを、長い歴史があった松島水族館がハブになっていくというのはとてもいい流れだと思います。
西條:そうなれることを願っています。あとはやっぱり、海と食というキーワードも切り離せないので、地元の漁師さんも絡めて、食育のプログラムなんかも取り入れたいと思っていますね。後継者不足に悩む地元の漁業を応援したいという気持ちもあります。

――震災以降に外部の人間が関わるようになって、新たな動きが生まれていることもあるのでしょうか。
西條:東北の人間って、どうしても閉鎖的になりがちな部分も強いので、そういう外部の流れは重要だと思います。最近では、少しずつ若い漁師さんも台頭してきている気がしますね。一方で、使われなくなってしまったカキの養殖場の処理施設を解放して、子どもたちの体験施設に使うとか、そうしたアイデアを今後はもっと広げていきたいと思っています。たとえばカキ棚をつくる昔ながらの技術があるのですが、それを70歳くらいのおじいさんが一人でやっていたりする。機械化もほとんどしていないので、広島の養殖所などと比べるとかなり遅れていますが、文化として残っている技術って、景色として見てもやっぱりいいんですよね。これからは、過剰に生産するのではなく、適正な量が適正な価格でまわるような仕組みをつくるやり方もあるんじゃないかと思うんです。
――地元に残っている文化をきちんと継承しながら、改良できることは改良する。そうして、地域の中で循環していく仕組みを子どもたちと考えていくことは、「地域の学び」においても非常に重要だと思います。
西條:松島でも、若い人は仙台や東京に流れてしまって、残っているのは地元の商店街とその一部くらいになってきていますからね。地域に根ざした学びでいうと、幸いにも松島は震災の被害も少ない場所でした。まだ生々しい記憶もある中、メモリアル的な記念碑をつくるかどうかという議論もあったのですが……、わたしたち松島水族館としては、88年間も続いてきたという歴史を踏まえて、当社の社長が長年かけて築いてきた漁師さんとのつながりや、業務外のことまで一生懸命に尽力してくれたスタッフやお客さんとの関係性を活かして、新たな受け皿を作りたいと思っています。いま考えていることのすべてをすぐに実現するのは難しいですが、この2年のうちに何らかのかたちにはしていきたいな、と。

――先ほどのお話にもあったように、生き物と直にふれ合う経験を残していく、ということでしょうか。
西條:「本能的に面白いこと」って、すごく大事なんですよね。それが学びにつながっていく。もっと、子どもたちには海で遊んでほしいと思いますね。津波の被害があったとき、どうしてもネガティブなイメージが払拭できず、海から子どもを遠ざけたいと感じる親御さんもいる。当然、ときに海は災害をもたらしますが、同時にわたしたちに恵みを与えてくれる存在でもあり。片方だけじゃなくて、どちらもある、ということを伝えていきたいですね。
- 取材:
- 3710LAB
- 文:
- 塚田有那


