-
レポート
2024.05.27

【開催報告】海とつながるエキシビション「OCEAN LEARNING」展
人イベントものづくりワークショップ海洋デザイン教育
-
レポート
2023.11.07

【開催報告】第二回国際海洋環境デザイン会議「OCEAN BLINDNESSー私た...
イベント海洋デザイン教育
-
コラム
2023.06.30

海洋環境デザインプロジェクトとは
環境デザイン海洋デザイン教育
-
レポート
2023.03.20

【開催報告】第一回国際海洋環境デザイン会議(2022年7月30日)
イベント環境デザイン海洋教育
-
連載
2023.03.13
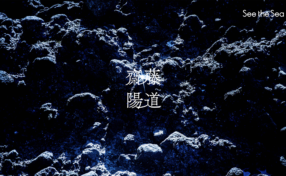
新連載「See the Sea」スタート
写真地域
-
連載
2023.03.13

za-boon.com をリリース!
ZaBoonデザイン
-
コラム
2019.06.26

海洋教育とは? 注目される理由と新学習指導要領での充実
学校探究学習海洋教育海洋デザイン教育
レポート

このシンポジウムは、3710Labメンバの田口が所属する東京大学海洋アライアンス海洋教育促進研究センターと日本財団の共催イベント。海と人との共生を掲げる海洋教育を促進するために、同センター、および、連携する全国の「海洋教育促進拠点」(教育委員会・学校・社会教育施設など)や海に関する学びに関心を示す団体が一堂に会し、その実践と成果の報告をするカンファレンスだ。
特に今年は、これまでの蓄積から基本的な海洋教育カリキュラムのモデルがまとめられた節目となる。そのため、それらを用いた実質的な「海洋教育の未来」について議論することが目的であると、筆者は受け取った。プログラムの構成は、これまでに実施した活動の報告と評価。それらをもとにしたパネルディスカッションでの「これからの海洋教育」についての議論。そして、実際にその教育を受けた小中高の生徒たちによるポスター発表だ。

アクティブな学び
まず、同センターの田中智志教授から「これからの海洋教育のビジョン」と題した報告が行われた。
これまでに実施した調査結果から「子供は海が好きだが、自分たちとのつながりを想像できない」ということが分かったという。例えば「海にまつわる仕事を想像できない」といったようなことだ。

その上で、これから目指すところを以下の3つに集約して、話がなされた。
1.海というテーマを通した学際的教育
2.素朴な問いに対する探求型教育:アクティブラーニング
3.よりよく生きることを目指す「存在論」的な教育
1の学際的教育は、自分と海とのつながりを感じるためにも、例えば理科に限らず、社会などの教科をも横断するカタチで、さまざまな事柄どうしのつながりを、海というキーワードを接点として学ぼうというものだ。
2は、単に知識を覚えることに終始するのではなく、自ら学ぶ姿勢を育てようというもので、海洋教育のみならず大学の学部教育でも広く試みられているアクティブラーニングだ。
この点に関しては、続いて行われたパネルディスカッションの冒頭でも、同センターの日置光久特任教授も触れていた。「そもそも学びとは ”アクティブ” なものだ。能動的でない学びは、本来存在しない」との旨、発言した上で、「アクティブに学ぶという、教育におけるHowの部分。この部分に焦点を絞りたい。新学習指導要領では、そこが問われている。」とした。また、このHowの部分は地域やテーマを越えて「海洋教育促進拠点」の間で共有しうるし、海洋教育以外の教育場面でも活用しうるものと言える。そういった、教育全般におけるモデルケースを作るという意気込みだろう。
「自分と自然とのつながりを発見しながら、自ら学ぶ」。このことを実現するために、1と2の指針の重要さは納得できる。

では、教育における存在論とは何か?
田中教授によれば、そもそも教育の概念は以下の2つに大別することができる。
(1)人間を作り変えることの支援
(2)人がよりよく生きるということを具現化すること = 存在論的な教育
同センターの海洋教育では、その重点を(2)に置いているよう見受けられる。センターのキーワードである「海とともに生きる」の「海とともに」は、よりよく生きることを具現化する、1つの方法を意味するからだ。
では、海との関係を見つめ直し、学ぶということは「我々がよりよく生きるという存在論」を、いったいどのように具現化するのだろうか。
海における存在論- それぞれの学び、それぞれの海

続くパネルディスカッションでは、連携する地方の教育委員会や学校など内、5団体がその報告をし、議論した。各活動の概要が紹介され、地域ごとの特色を活かそうとしていることもよく分かった。
しかし、筆者が感じるのは、そして、筆者が小中高の時代に感じていたことは、一人一人、求めるものも感じ方も違うということだ。教師たちがそれぞれに頑張っていることも分かる。しかし、「カリキュラム」という存在自体が、画一的で、同調圧力的で、「アクティブ」ではない。そう感じていた。このもどかしさは、どうすれば良いのだろうか。
少し、時間を遡る。
2015年の夏、3710Labを立ち上げるに際し、我々は仙台を中心に取材(松島水族館、うみの杜水族館 など)を行い、最後にディスカッション型のトークイベントを行った。
https://www.facebook.com/events/856572514396017/
ゲストは、さまざまな立場から海や地域に関わる人々。震災後に東京大学広報から東北大学に移り、被災地取材を続ける清水修 氏。せんだいメディアテークや個人の活動としてさまざまな企画を続け、震災関連の活動などにも携わる小川直人 氏。自身も被災者であり、自宅が流された荒浜地区で「海辺の図書館」を始めた庄子隆弘氏。生物との「共同制作」により生物と人との関係を描き出すアーティスト AKI INOMATA 氏。以上4名のゲストと、仙台や松島など近隣地域からの参加者でディスカッションを行った。

そこで、さまざまな立場から、さまざまな議論を経て分かったことは、それぞれの人が描く「海のイメージ」と、海との物理的・心理的「距離感」が異なるということだった。特に、震災などに関しては、当事者性の強さも千差万別という現実がある。
つまり、ここで感じたことも、よりよく生きるための海との関係について、対象となる「海」も違えば、「関係性」も人それぞれ異なるということであった。
この(ある種当たり前すぎる)現実を前にして、教育という現場で、私たちはどのように生徒たちに「海」を提示すれば良いのだろうが。
そのようなことを感じながら、シンポジウムの前半を過ごしていた。正直なことを言えば、壇上で語られる海洋教育が、その重要性とストラテジーについて、抽象的なレベルで同意できるものの、どこか、具現化し得ていないもののように聞こえていたのだ。
しかし、その印象は、この後のポスターセッションにてひっくり返されることとなった。それは特に、児童、生徒たちの研究発表を聞いたことによっている。その詳細については、後半部分のレポートをご覧いただきたい。

- 文:
- 菅野康太


